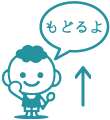2025年2月のマラウイでの活動についてご報告します。
1. 天皇誕生日祝賀会(在マラウイ日本大使館)
2025年2月20日、せいぼマリアは在マラウイ日本大使館の招待を受け、リロングウェのBICCで開催された日本国天皇誕生日祝賀会に参加しました。せいぼマリアを代表して、Victor、Future、Mwaiの3名が出席しました。このイベントは、政府関係者、企業パートナー、外交関係者とのネットワーキングの貴重な機会となりました。
せいぼマリアは、バナーやプロジェクターを使用した展示ブースを設置し、活動内容を紹介しました。イベントでは、大矢大使やNancy Tembo 大臣などの要人によるスピーチが行われ、日本がマラウイにもたらしてきた貢献が強調されました。また、文化パフォーマンスや伝統的な鏡開きの儀式も披露されました。
 せいぼスタッフの様子
せいぼスタッフの様子

大矢大使(在マラウイ日本国大使)とせいぼスタッフ
2. せいぼ誕生9周年記念式
2月11日、せいぼの9周年を迎え、SNS上で記念の投稿を行いました。本格的な記念式典は2月28日にブランタイヤで開催されました。
記念イベントの一環として、Kriver幼稚園で給食調理実演を行い、せいぼのスタッフ、理事、近隣の学校の校長が参加し、せいぼの理事が子どもたちに給食を提供する特別な機会となりました。
食事の後、理事のDhlelisile Phiri 氏がケーキカットのセレモニーを行い、子どもたちは楽しそうに「ハッピーバースデー」の歌を歌いました。参加者全員でケーキを分け合い、忘れられないひとときを過ごしました。



「近隣の幼稚園の校長たちが給食調理実演会に参加し、学校給食プログラムへの献身と責任感を示しました。栄養が教育と子どもたちの健やかな成長にとっていかに重要であるかを改めて強調する機会となりました。」

「せいぼのプログラムマネージャーであるVictor Mthulo氏に、温かい給食を提供できたことを光栄に思います。これは、彼の組織への献身に対する感謝の気持ちを表すものでした。」(Kriver幼稚園にて撮影)

給食の準備をするせいぼの理事とプログラムマネージャー

給食を食べる校長たち

ケーキカット後の子どもたちの様子

子どもたちに給食を提供した後、給食を食べる理事とプログラムマネージャー
3. 学校長会議
記念式典の後、午後にはMary Queen of Peaceホールにて学校長会議を開催しました。議題には、新しい帳簿の適切な記録手順、給食の適切な調理方法、給食原料の安全な保管方法、学校内での盗難などの緊急事態への対応プロトコルなどが含まれました。また、既定の手順や標準作業手順(SOP)に従わなかった場合の影響についても説明されました。
会議後、学校に調理器具を配布し、集合写真を撮影して閉会しました。




「せいぼのチーム、校長、学校委員会、教師たちが一堂に会し、会議の後にせいぼじゃぱんへの心からの感謝の意を表しました。」(St. Kizito小学校にて撮影)
4. 日本からの視察スタッフの訪問
せいぼじゃぱんが実施する日本での教育プログラムで出会った米山翔さんが、マラウイの給食支援現場を訪れてくださいました。
現地の給食支援の様子を観察して下さり、マラウイの人々との交流を通して、現地と日本の間の絆を深める上で、積極的な効果をもたらしてくれたと思います。
今後も、日本での学校教育プログラムにも、米山さんからのご報告やご経験内容を生かしていければと思います。



5. 学校給食プログラムへの感謝(学校関係者の声)

「このプログラムは、単に給食を提供するだけでなく、子どもたちが遊びやダンス、その他の表現活動を通じて創造性を育む機会も提供しています。総合的な教育と成長を促す貴重なプログラムです。」(Kriver幼稚園にて撮影)

「せいぼのチームは、世界中のお腹を空かせた子どもたちに食事を届けるという使命の達成に向けて、力強く取り組んでいます。」(Kriver幼稚園にて撮影)
 「空腹の子どもたちは、不機嫌になりがちです。一方、栄養のある温かい給食を食べた子どもたちの明るく幸せそうな表情は、その満足感を物語っています。」(St. Kizito小学校にて撮影)
「空腹の子どもたちは、不機嫌になりがちです。一方、栄養のある温かい給食を食べた子どもたちの明るく幸せそうな表情は、その満足感を物語っています。」(St. Kizito小学校にて撮影)
 「学校給食プログラムの成功は、適切な衛生習慣の維持が鍵となっています。特に現在は雨季であり、コレラの流行が懸念されるため、手洗いの徹底が水系感染症の予防に不可欠です。」(Tinashe幼稚園にて撮影)
「学校給食プログラムの成功は、適切な衛生習慣の維持が鍵となっています。特に現在は雨季であり、コレラの流行が懸念されるため、手洗いの徹底が水系感染症の予防に不可欠です。」(Tinashe幼稚園にて撮影)

「保護者たちは、この給食プログラムが子どもたちの成長を支えていると高く評価しています。学校で提供される給食が子どもたちの登校意欲を高め、健康的に成長する助けとなっていると述べています。」(Kriver幼稚園にて撮影)

「この10歳の少年にとって、給食は単なる食事以上の意味を持っています。『学校に行けばお粥がある、それが楽しみで毎日通っています』と彼は語ります。『大きくなったら先生になりたいです』と自信を持って話していました。」(Kabuku小学校にて撮影)
2025年2月の給食記録
給食支援データ(2月)
合計支援給食数:346,542食
北部ムジンバ地区:318,719食
南部ブランタイヤ地区:27,823食